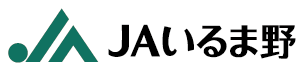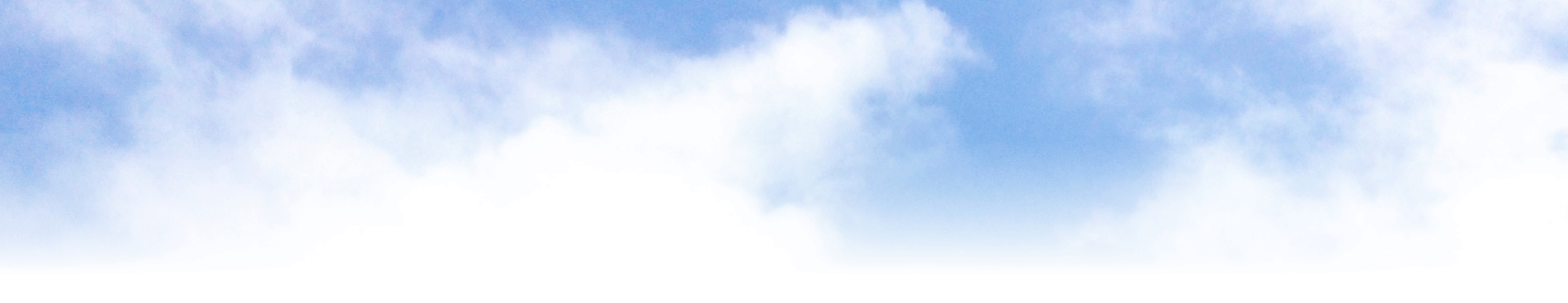
いるま野NEWS
トップ
梅の人工授粉を行う
2025年3月25日

梅の産地として知られる越生町で3月10日、JAいるま野越生支店梅部会は、同町の2024年産梅の収量減少を受け、25年産梅の着果量向上を目的に、梅の人工授粉の講習会を開きました。同町で梅の人工授粉を行うのは初の試みです。
24年産は2月末から3月上旬に寒さが戻り、梅の品種ごとに開花時期にズレが生じたことや、開花時期の降雨の影響でミツバチの活動が停滞するなどの要因から、受粉に支障が出たと考えられます。着果量を増やすため、人工授粉を試みようという声が生産者や町からあがり、講習会の開催に至りました。
当日は同部会の横田会長の圃場(ほじょう)と、山口農園の山口代表の圃場で人工授粉を実施。同部会員や、武蔵越生高校の生徒ら約40人が参加しました。高校生は地域貢献活動の一環として、梅の振興を図ろうと人工授粉の作業を手伝いました。
川越農林振興センターの関口主任が講師を務め、人工授粉の注意点や、着果量を増やすための対応策を紹介。バケツに挿した受粉枝の配置場所や、別品種の高接ぎの手法など、実践を交え説明しました。
人工授粉には、ポリエステルやダチョウの毛を使用した、長さ約30センチ~約2メートルの毛ばたきを使用。毛ばたきで「越生べに梅」などの梅の花を撫でて花粉を採取し、別品種の「白加賀」の梅の花に付着した花粉を押し当てる作業を繰り返し行いました。
関口主任は「人工授粉をすることで、まずは着果量を増やしたい。梅が受粉できる環境づくりを心がけてほしい」と呼び掛けました。
横田会長は「1粒でも多く収穫できるよう人工授粉を行い、みんなで試行錯誤しながら取り組んでいこう」と意気込みました。
高校生は「越生町のために少しでも力になりたい。丁寧な作業を心掛けていきたい」と話しました。
山口代表は「高校生の協力もあり、人工授粉はスムーズに行えた。少しでも着果量が増えるよう、みんなで力を合わせて産地を守っていきたい」と話しました。
人工授粉の成果は、早ければ4月の中旬から現れます。